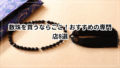\今話題の商品をランキングでチェック!/ 楽天ランキングページはこちら /欲しいが見つかる!楽天市場ランキングから厳選おすすめ!\
郵便物の配達状況を確認したときに「持ち出し中」と表示されることがあります。
これは、荷物が配達員の手に渡り、今まさに配達されようとしている状態を指します。
本記事では、この「持ち出し中」が意味することや確認方法、配達に関わるさまざまな情報について詳しく解説します。
郵便局持ち出し中とは?
持ち出し中の意味と状況
「持ち出し中」とは、郵便局の配達員が荷物を手に取り、配達先に向かって実際に配達作業を行っている状態を指します。
このステータスが表示された時点で、荷物は集配局や配送センターをすでに出発しており、配達ルートに沿って順番に届けられている途中段階です。
配達員が多くの荷物を同時に持ち出していることもあるため、特定の荷物が何時頃届くかは前後することがありますが、一般的には配達が差し迫っている段階と考えて良いでしょう。
いつ届くのか?
「持ち出し中」の表示が確認できた場合、原則としてその日のうちに配達されることが期待されます。
特に時間指定がなければ、配達ルートに基づいて順次届けられるため、午前中から夕方にかけての間に配達が完了することが多いです。
ただし、配達員のルートの都合やその日の荷物量、天候の変化、道路状況(渋滞・工事)などによって、配達が遅延する場合もあります。
また、時間指定がされている場合は、その時間帯を優先的に守るため、ルートの順序が変更されることもあります。
荷物の持ち出し状況を理解する

日本郵便の追跡サービスでは、荷物のステータスが段階的に表示される仕組みとなっており、「持ち出し中」は配達直前のステップにあたります。
この表示が出た段階では、すでに配達員の手に荷物が渡っており、あとは受取人のもとに届けられるだけの状態です。
もし「持ち出し中」の表示が長時間変わらない場合は、配達中に何らかのトラブルが発生している可能性もあるため、状況によっては郵便局への問い合わせを検討すると良いでしょう。
郵便局の持ち出し中確認方法
電話で確認する方法
最寄りの郵便局に電話をかけ、追跡番号(お問い合わせ番号)を伝えることで、荷物の詳細な配達状況をオペレーターが確認してくれます。
特に「持ち出し中」が長く続いている場合や、ステータス更新が止まっている場合には、電話での問い合わせが有効です。
電話対応の受付時間は局によって異なることがあるため、事前に郵便局の営業時間を調べておくとスムーズです。
ただし、昼休みや夕方などの混雑時間帯は電話がつながりにくくなる傾向があるため、午前中の早い時間帯に連絡するのがおすすめです。
また、自動音声応答による案内が導入されていることもあり、音声ガイダンスに従って適切なメニューを選択する必要があります。
追跡番号の活用法
日本郵便の公式ウェブサイトにある「追跡サービス」では、荷物に付された追跡番号を入力するだけで、配達ステータスの確認が可能です。
ステータスは「引受」「発送」「到着」「持ち出し中」「配達完了」などの段階に分かれており、いつ・どこで処理されたかが時系列で表示されます。
また、配達済みの荷物には、配達完了日時や受取人情報の記録が表示される場合もあるため、確認に役立ちます。
アプリやウェブサイトでのリアルタイムチェック

スマートフォン向けの日本郵便公式アプリを使うと、追跡番号を登録しておくだけでステータスが自動更新され、通知で知らせてくれます。
さらに、LINE公式アカウントと連携させれば、チャット形式で追跡情報を手軽に確認したり、再配達依頼をその場で行ったりすることも可能です。
アプリやウェブサイトを活用すれば、外出先でもリアルタイムに荷物の現在地を確認できるため、忙しい日常の中でも安心して配達状況を把握することができます。
持ち出し中の配達状況
予定と実際の配達時間の違い
予定された配達時間が表示されていても、実際の配達はその時間通りに行われない場合が多々あります。
これは、天候の急変や交通渋滞、道路工事などの外部要因が影響するだけでなく、その日の配達件数やルートの見直しなど内部的な理由も関係しています。
特に、同じ地域内でも複数の住所を担当している配達員が、一件ごとの滞在時間や不在対応の時間などによってスケジュールにずれが生じることがあり、全体の時間配分が変動します。
配達時間の目安はあくまで参考情報と捉え、柔軟に対応することが大切です。
配達員の状況と遅延の可能性
配達員の担当区域の広さや地形、建物の構造、配達物の件数などは、配達効率に大きな影響を与えます。
例えば、集合住宅でのインターホン操作や、エレベーター待ちが頻発する場合、1件あたりの配達時間が延びる要因になります。
また、急な欠員による応援体制や、新人配達員の教育期間中などは配達スピードが落ちることもあるため、「持ち出し中」から配達完了までに想定以上の時間がかかる場合もあります。
再配達手続きの流れ
不在時には、配達員が不在票を投函し、荷物は郵便局に持ち帰られます。
不在票には、再配達の申し込み方法(電話・インターネット・スマートフォンアプリ)と、再配達可能な時間帯が記載されており、これに従って再配達を依頼します。
また、再配達を依頼する際には、追跡番号や希望する時間帯を入力・伝える必要があり、これによりスムーズな再配達が実現します。
近年では、QRコードを読み込むだけで再配達手続きが完了するサービスも増えており、利便性が向上しています。
持ち出し中に影響する要因
繁忙期の影響
年末年始やゴールデンウィーク、夏季休暇などの大型連休、さらにはブラックフライデーや年末セールの時期になると、ネット通販の利用者が増加し、配達量も急激に増えます。
このような繁忙期には、一人の配達員が処理する荷物の数も大幅に増えるため、通常よりも配達時間が遅れる傾向があります。
また、再配達依頼も多く寄せられるため、同じルートで複数回訪問することもあり、効率が下がる要因になります。
さらに、短期アルバイトの配備や応援体制が取られることもありますが、それでも対応しきれないケースも存在します。
そのため、繁忙期には通常より余裕を持った受け取りのスケジュールを立てることが望まれます。
交通渋滞や天候の要因
都市部では慢性的な渋滞が発生しやすく、特に通勤時間帯や週末の昼間などは移動に大きな時間がかかります。
これに加えて、大雨や台風、大雪、猛暑などの異常気象が発生すると、道路の通行規制や事故によって配達の遅延が生じます。
冬季の降雪地域では、積雪による道路の封鎖や配達車両の立ち往生といったトラブルも発生しやすく、持ち出し中であっても一時中断されるケースがあります。
気象条件は人の力ではコントロールできないため、事前に天候情報を確認し、配達の遅延リスクに備えておくと安心です。
システムの問題とその対策
日本郵便では、追跡情報やステータス更新を管理するためのITシステムを導入していますが、このシステムにおけるメンテナンスや障害が発生することで、情報の更新が遅れることがあります。
たとえば、持ち出し中に変更されるはずのステータスが更新されない、実際には配達済みなのに追跡上では未配達と表示される、といった現象が起こることもあります。
こうしたトラブルに対しては、日本郵便が公式サイトで情報を発信したり、コールセンターを通じた問い合わせ対応を行うことで、状況の把握と解決を支援しています。
また、予期せぬ障害に備えて、複数の確認手段(アプリ、公式LINE、電話など)を用意しておくと、より安心して荷物の状況を確認することができます。
配達中や不在票について
不在時の荷物の取り扱い
不在時には、配達員が荷物を一度持ち帰り、担当の郵便局で一時的に保管されます。
この場合、ポストに「ご不在連絡票(不在票)」が投函され、その票に記載された方法で再配達の手続きを行う必要があります。
郵便局での直接受け取りを希望する場合も、不在票を持参して窓口で提示することで対応してもらえます。
また、保管期限を過ぎると荷物は差出人へ返送されるため、早めの対応が大切です。
不在票の意味と確認方法
不在票とは、配達時に受取人が不在だった場合に配達員がポストに投函する通知票です。
この票には、配達員の訪問日時や荷物の追跡番号、再配達の依頼方法(電話・ネット・アプリなど)、そして荷物の保管期限が記載されています。
QRコードが印刷されていることも多く、それを読み取ることで簡単に再配達依頼ページにアクセスできます。
LINE公式アカウントからの操作や、日本郵便のスマートフォンアプリを活用することで、手軽かつ迅速に手続きが行えます。
再配達依頼の必要性
一度不在となった荷物は自動的に再配達されるわけではありません。
再配達を希望する場合、必ず利用者自身が日時や方法を指定して申し込む必要があります。
電話・インターネット・スマートフォンアプリなど複数の手段が用意されており、受け取りやすい日時を柔軟に選ぶことが可能です。
なお、何度も不在が続くと配達保管期間の終了を迎え、荷物が差出人に返送されるリスクもあるため、早めの対応が推奨されます。
郵便局に連絡するタイミング
いつ電話すべきか
「持ち出し中」のステータスが長時間続いているにもかかわらず荷物が届かない場合や、不在票がポストに入っていないと感じた場合は、郵便局への連絡を検討しましょう。
特に、配達予定日を過ぎても配達が完了しない場合や、荷物の追跡状況が更新されないケースでは、何らかのトラブルが発生している可能性があります。
また、配達員の手違いや誤配の可能性も考えられるため、早めの確認が安心につながります。
問題発生時の対処法
荷物の紛失や破損が疑われる場合、追跡番号を手元に準備したうえで、最寄りの郵便局または配達を担当する集配局に連絡を取りましょう。
連絡の際には、配達予定日や現在の追跡ステータスなど、できる限り詳細な情報を伝えると調査がスムーズに進みます。
万が一、調査の結果として紛失や損傷が確認された場合は、補償対応などの手続きも必要となるため、事前にガイドラインを確認しておくと安心です。
必要な情報を把握する
電話連絡をする際は、スムーズに状況を説明できるよう以下の情報を事前に整理しておきましょう。
- 荷物の追跡番号(お問い合わせ番号)
- 送付先・差出人の氏名と住所
- 荷物の内容やサイズ、形状などの特徴
- 可能であれば発送日や配達予定日
これらの情報を的確に伝えることで、対応が迅速かつ正確になり、問題解決までの時間短縮にもつながります。
持ち出し中の荷物の地域差
地域による配達状況の違い
都市部では交通網が発達しており、配達員の人数も多いため、1日に複数回の配達が行われることもあります。
その一方で、地方や山間部では配達ルートが長距離になりがちで、配達回数が少なく、1日1回の配達が基本となる地域もあります。
そのため、同じ「持ち出し中」の表示でも、実際に配達されるまでの時間には地域差が生じます。
住所や受け取り方法の影響
マンションやアパートなどの集合住宅では、オートロックや宅配ボックスの有無が配達効率に大きく影響します。
宅配ボックスが設置されている場合は、配達員が直接手渡しする必要がないため、不在時でもスムーズに荷物を届けることが可能です。
一方、戸建て住宅やオートロックのない建物では、在宅確認が必要なため、時間がかかるケースもあります。
また、受け取り方法として「対面受け取り」を希望している場合、配達時間に家にいなければならないため、配達タイミングの調整も必要になります。
特定の地域における配達頻度
市街地や人口の密集した地域では、配達件数が多いためルートが最適化されやすく、効率的な配達が実現されています。
しかし、農村地域や離島などでは、配達員の巡回頻度自体が少なく、曜日によっては配達がない場合もあります。
また、自然災害が起こりやすい地域や、冬季に積雪が多いエリアでは、持ち出し中であっても安全確認のために配達が遅れることがあります。
そのため、地域ごとの事情を把握しておくことが、荷物の到着時間に対する理解を深める助けになります。
配達の遅延について知っておくべきこと
遅延の原因とは?
天候の急変や交通渋滞、年末年始や大型連休中の繁忙期などは、配達業務に大きな影響を及ぼします。
また、住所の記載ミスや不明確な表記、建物名の欠落なども配達先を特定できず、再確認が必要になるため、遅延の一因となります。
このほか、配達ルートの見直しや交通規制、地域による配達員の人数不足なども複合的に影響します。
配達員の仕事内容とその役割
配達員は毎日数十件から数百件の荷物を担当エリア内で効率的に届ける責任を担っています。
ただし、配達ルートの状況や階層の高い建物が多いエリアでは、時間がかかる場合があります。
加えて、再配達の手続きや不在時の対応、問い合わせ対応なども並行して行っているため、業務負担が大きく、予定通りの配達が困難になることがあります。
遅延時の対応策
配達が遅れていると感じた際は、まずは追跡番号を使って配送状況を確認するのが基本です。
追跡情報が「持ち出し中」で長時間変わらない場合や、不在票が見当たらない場合は、最寄りの郵便局へ直接問い合わせを行いましょう。
また、配達に関して疑問がある場合は、公式アプリやWEBサイトにあるチャットボットや問い合わせフォームを活用することもできます。
より早い対応を希望する場合には、電話による問い合わせが有効です。
郵便物と荷物の違い
郵便物の一般的な扱い
手紙やはがきなどの郵便物は、ポストに投函することで配達が開始され、多くの場合、翌日以降に届けられます。
速達サービスを利用することで、より早い配達が可能になり、重要書類や急ぎの手紙に多く利用されています。
また、書留郵便や配達記録郵便といったオプションを付けることで、郵便物に対して一定の追跡機能や補償が付与される場合もあります。
荷物宅配のプロセス
ゆうパックやレターパックなどの荷物は、集荷依頼または郵便局窓口での預け入れにより発送されます。
荷物は集配センターで仕分けされ、各地域の配送拠点へと移動し、配達員によって受取人の元へ届けられます。
この一連の流れはすべて追跡可能で、ステータスが段階ごとに更新されるため、現在の所在や状況を把握しやすくなっています。
それぞれの配達状況の把握
郵便物には通常追跡機能がなく、投函後の状況を確認することはできませんが、書留や特定記録などのオプション付き郵便物は例外です。
一方、荷物については、発送から配達までのすべてのステータスが明確に表示されるため、安心して管理できます。
特に再配達や配達済みの確認などにも役立ち、受け取りのタイミングを事前に把握することが可能です。